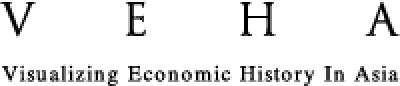アジア地域におけるモノ・人・資金のフローや、それらにたずさわる商人や金融機関のネットワークを可視化することは、それ自体、有効な分析手法であると考えられる。それらの態様と時系列での変化は、可視化することによってよりよく理解できる可能性も高いし、文献や統計からだけでは分からない、相関や変化のパターンを発見できることも考えられる。 更に、可視化された経済情報を、自然地理(気候、地形、水系等)、政治・行政区画、社会経済地理(土地利用、人口分布、宗教言語等)などに関する様々な地理上の配置・分布(ランドスケープ)と重ね合わせてみることは、つとに指摘されているアジアの多様性との関係から、そこでの経済について理解することにつながるであろう。
Visualizing the flows of goods, people, and capital in Asia as well as the networks of merchants and financial institutions that are involved in them can be in itself an effective analytical method. We may better understand changes in their forms and chronological developments and find patterns of correlation among them that cannot be deciphered from conventional analysis of archives and statistics. Furthermore, mapping economic information onto the various kinds of landscapes, such as those of physical geography (climate, topology, water systems, and so on), of political and administrative divisions, and socio-economic geography (land use, population distribution, religion, language, and so on) will enable us to examine the economy of Asia in terms of the great deal of diversity in the area.
経済情報を可視化するに際して、「一目瞭然」に図示するといったことは、その狙いの半分に過ぎない。経済情報に空間上の特定の地点又は区域の位置を示す空間IDをつけることによって、すべてのデータは空間IDを介して、時系列上も、地点間でも、異なる問題に関する情報間でも、相互に参照可能となる。そうした上で可視化された経済情報を相互に重ね合わせる、或いは様々な特性に基づいて描かれた地図上に開示してみる、という作業は、空間情報の相互の相関性に関する仮説を構築し、検証するという空間解析を、経済史研究に応用する試みとなっている。
In visualizing economic information, demonstrating it as “comprehensible at a glance” is just one half of the aim. By attributing spatial ID to economic information regarding its specific location or its area, all data can be cross referenced through the spatial ID on the chronological series, between geographical locations, and among information on different issues. In this regard, in the study of economic history, over-layering visualized economic information or projecting it on the maps of various characteristics constitutes the key attempt in the spatial analysis, namely to build and test hypotheses regarding correlation among spatial information.
従来、非ヨーロッパ地域の統計は不完全なことが多く、数量分析を一つの柱とする経済史研究を行う上での障害となってきた。近年、大量のデジタル歴史資料が検索機能を備えた形で公開されたことは、研究環境の大きな変化である。統計を探す、のではなく、同時代資料から数値データを抽出して統計資料を作ること、または大量の文献資料から数量分析の対象となるデータベース(DB)を作成することが可能になっている。欧米経済史では既に、大規模DBを利用して、13世紀から20世紀の間のイギリスにおける物価動向や、13世紀から18世紀の金貨・銀貨のストックの推計など様々な実証研究が行われつつある(Mark Casson and Nigar Hashimzade eds., Large Databases in Economic History, 2014等)。 また、コンピューター・グラフィックCGやGISを始めとする情報の可視化技術の社会科学への応用は、経済史、歴史地理学、情報工学、コンピューター・サイエンス等が交差する、新たな研究のフロンティアとなっており、単なる図示を超えた分析手法としての可能性が模索されている(Ian Gregory and Alistair Geddes eds., Toward Spatial Humanities, 2014等)。 こうした最新の研究潮流を背景とする、可視化を通じた新たな研究の視角・手法の構築を目指すに当たって、パイロットケースの一つとして、「世界貿易の多元性と多様性:「長期の19世紀」アジア域内貿易とその制度的基盤」(科研費基盤研究A、H24-27年度、代表:城山智子)の成果の一部を示す。18世紀後半から第一次大戦までの「長期の19世紀」には、域内で生産された農作物・軽工業品を中心に多角的に貿易が展開された。そこでは、生産拠点、交通手段、流通のハブなどの、様々な空間的配置の変化が生じていた。ここでは、空間情報に関する実証研究の成果を示すだけではなく、経済・空間データベースの構築、コンピューター・グラフィック(CG)や地理情報システム(GIS)を利用した可視化、貿易の空間分布とその時系列的変化の分析という、データ・メソッド・解析を一つのパッケージとして提示していく。
Because statistics from non-European areas are often incomplete, quantitative analysis of their economies often faces obstacles. In this context, it is a huge change in the research environment in recent years that large amount of digitized historical material with a search function has become available. Rather than looking for statistics, it is now possible to generate statistical material by extracting quantitative data from contemporary materials and to create a database (DB) from a vast amount of literature for quantitative analysis. In the economic history of the West, a range of empirical studies using large-scale DBs are already being carried out, including one on the trend in prices in Britain between the thirteenth and twentieth centuries and another one on the estimation of gold coin and silver coin stocks from the thirteenth to eighteenth century (see, for instance, Mark Casson and Nigar Hashimzade eds., Large Databases in Economic History, 2014).
In addition, the application of visualization techniques including computer graphics (CG) and Geographic Information System (GIS) to social sciences constitutes a new frontier for research where economic history, historical geography, information technology, and computer science interact. As such, the technique’s capacity as an analytical method of going beyond mere visual presentation is also explored (see, for instance, Ian Gregory and Alistair Geddes eds., Toward Spatial Humanities, 2014).
Here, we present—as one of the pilot studies—in our endeavor to construct a new research perspective/method through visualization against the backdrop of the latest developments in research, some of the outcomes of our project, “The plurality and diversity in global trade: Intra-Asian trade during the ‘long nineteenth century’ and its ‘institutional bases’” (Scientific Research A, Grant-in-Aid for Scientific Research, 2012-2015, PI: Tomoko Shiroyama). Multi-faceted trade centering on agricultural produce and light industrial goods produced in the area flourished in the “long nineteenth century” from the mid-eighteenth century till World War I. There were a variety of changes in spatial configurations of production bases, transport methods, and distribution hubs. We present here not only findings from our empirical research into spatial information but also research processes
as a package, consisting of the construction of economic and spatial databases, visualization using CG and GSI, and analysis of the spatial distribution of trade and changes in its chronology.
The visualization analysis of Asian regional trade has been pursued through interdisciplinary collaboration among economic historians, GIS experts, and media designers. Below is the list of members of the research team and their roles and expertise.
- 城山智子 (東京大学経済学研究科):統括・中国関係DB
- Tomoko Shiroyama (Graduate School of Economics, University of Tokyo): Overall coordination; Databases related to China
- 島西智輝(東洋大学経済学部):統括・コーディネーター
- Tomoki Shimanishi (Faculty of Economics, Toyo University): Overall coordination
- 木越義則 (名古屋大学経済学研究科):中国関係DB
- Yoshinori Kigoshi (School of Economics, Nagoya University): Databases related to China
- 小林篤史 (日本学術振興会特別研究員):東南アジア関係DB
- Atsushi Kobayashi (Research Fellow, Japan Society for the Promotion of Science): Databases related to South East Asia
- 小川道大 (東京大学人文社会科学研究科研究員):インド関係DB
- Michihiro Ogawa (Research Fellow, Graduate School of Humanities and Sociology, University of Tokyo): Databases related to India
- 神田さやこ (慶應義塾大学経済学部):インド関係DB
- Sayako, Kanda (Faculty of Economics, Keio University): Databases related to India
- 高橋昭子 (てくてくGISラボ、代表):GISによる可視化
- Akiko Takahashi (TekuTekuGIS Lab., President): Visualization by GIS
- 脇田玲 (慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科):メディア・デザイン
- Akira Wakita (Faculty of Environment and Information Studies, Keio University): Media design
- 長島禎 (慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科):メディア・デザイン、ホームページ作成
- Tadashi Nagashima (Research student, Faculty of Environment and Information Studies, Keio University): Media design; creation and maintenance of the web site